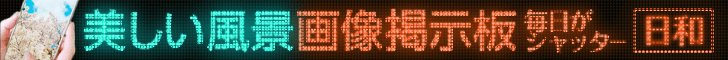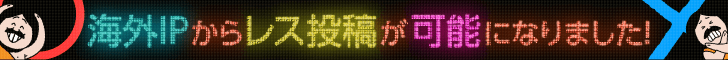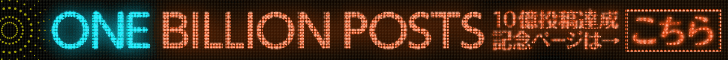中国でメーデーの小型連休に短距離旅行や省をまたぐ旅行、県エリアに出かける県域旅行、海外旅行など複数の旅行のスタイルが人気を集め、複数のオンライン旅行予約プラットフォームで景勝地のチケット予約に「小さなピーク」が現れ、中国国内の観光市場は「量も価格も」上昇した。専門家は、「メーデー連休に消費市場の活力と内需のポテンシャルが発揮されたことが、これから経済の安定・好転をけん引する上でプラスになるだろう」と分析した。
出入国者が延べ800万人以上に
中国国家移民管理局は6日、「統計によると、今年のメーデー連休に全国の国境検査所が前年同期比35.1%増となる中国内外の延べ846万6000人の出入国検査を行った。1日当たりの出入国検査のピークは5月3日で、人数は延べ180万1000人に達した」と伝えた。
同連休中、中国の観光客が世界のあらゆる場所に出かけた。旅行予約サイトの「Qunar.com」のデータを見ると、今年の同連休には、国際線の航空券と海外のホテルの予約件数がどちらも同期の過去最高を更新した。
海外旅行の面では、同連休中に中国の観光客は世界200カ国近くの3000を超える都市に出かけ、東南アジア、日本、韓国といった近場の国が人気だった。
インバウンドの面では、同連休のインバウンド予約件数は同105%増加した。中国がビザ免除対象国とした12カ国や中国と相互にビザを免除するシンガポールとタイからのインバウンド観光客は累計で前年同期比約2.5倍増になった。
また、Qunarのデータによると、今年の同連休に、国際線航空券と海外ホテルの予約件数がどちらも同期の過去最高を更新した。中国の観光客は世界の1035都市に出かけていた。中国の観光客の集中的な動きが世界各地の消費の回復をけん引した。
県域旅行が思いがけず人気に
携程旅行網のデータによると、今年の同連休の旅行予約の前年同期比成長率は三線・四線都市が一線・二線都市を上回り、県域市場が三線・四線都市を上回った。安吉、桐廬、都江堰、陽朔、弥勒、義烏、婺源などの県域観光地が人気で、予約件数は平均で36%増加した。
携程研究院の王亜磊(ワン・ヤーレイ)業界アナリストは、「三線以下の都市は(比較の対象となる前年同期の)基数が低く、成長の可能性がより大きい」とした上で、「一線・二線都市がどこへ行っても混んでいるのに比べ、三線以下の都市の観光市場はより快適でリラックスできる。また県域の観光市場での消費は観光客にとってよりコストパフォーマンスが高いものになる」との見方を示した。
このほか、移動交通スタイルの変化も県域旅行の思いがけない人気を促進した客観的な原因となった。中国交通運輸部によると、今年の同連休には社会全体の地域をまたぐ人の移動が1日当たり延べ2億7000万人を超え、このうち運転での移動の割合が80%を超えた。(提供/人民網日本語版・編集/KS)
 ポスト
ポスト