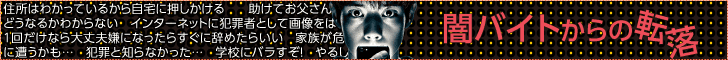長野県松本市の一般貨物自動車運送業者の「翔進」が2月10日付けで事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。
民間の信用調査会社・帝国データバンク松本支店によりますと、同社は2005年12月に設立された一般貨物自動車運送業者で、主に傭車として冷凍食品など食料品を主体とした運送を手掛けていたということです。
しかし、従前より収益性は乏しく、財務面は債務超過に陥っていたなか、新型コロナウイルスの感染拡大時には受注は減少し、新型コロナ対策融資や持続化給付金によりしのいでいたということです。
感染緩和により、トラックを増車して受注は回復をみせましたが、高齢化が進むトラックドライバー不足に伴う人件費の上昇や燃料高騰を価格転嫁しきれずに資金繰りはひっ迫し、2024年4月からはトラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用されたことで人手不足が深刻となり、先行きの見通しが立たないことから事業の継続を断念したということです。
負債は調査中ですが、約4500万円を上回るとみられています。
[匿名さん]
長岡市の闇会社で有名なトライオテック株式会社
工場新設、人材募集しているが大丈夫なのか?
[匿名さん]
アプトシステムズの社長は中国人。HPを見たら南陽にあるシナノ精機(米谷竜也代表)と関連会社。となると、闇が深い。真相を教えて下さい。
[匿名さん]
U字溝や擁壁などのコンクリートの二次製品の製造を主に手掛けていた、新潟県柏崎市西山町の『永井コンクリート工業』が、21日に新潟地方裁判所から破産手続き開始決定を受けていたことがわかりました。
負債総額は約19億3079万円に上るとみられています。
民間の信用調査会社の帝国データバンクや東京商工リサーチによりますと、1931年に創業した『永井コンクリート工業』は、地中に埋設する「ボックスカリバート」や「ハンドホール」と呼ばれるコンクリート製二次製品の製造を得意とし、“ボックスカルバートの永井”として新潟県内で相応のシェアを有していました。
加えて新潟県内のみならず青森県にも営業所や工場を擁し、原子力発電所の工事に特化した受注もこなしつつ、生コンクリート販売なども手掛け、汎用品から特注品まで対応する幅広い製品を供給できる体制を構築し、2009年3月期には22億8700万円の年売上高を計上しています。
[匿名さん]
住宅の水道施設工事から、砂防や道路などの公共工事まで幅広く手掛けていた越前町梅浦の「中西」が、破産手続き開始決定を受けていたことが分かりました。
民間の調査会社・帝国データバンクや東京商工リサーチによりますと、「中西」は1957年に創業し、1992年に法人化した越前町周辺を施工エリアとする土木工事業者です。
住宅の水道施設工事から、砂防工事や道路改良工事、護岸工事などの公共工事の実績もあり、ピーク時の2008年6月期には2億900万円を売り上げていました。
しかし、公共工事などの受注が減少し、外注工事が中心となり、安定した収益確保が難しくなったことから、2010年6月期には赤字を計上し債務超過に陥りました。
その後も売り上げの回復には至らず、2013年9月には福井信用保証協会による代位弁済が実行されるなど先行きの見通しが立たず、2018年9月には従業員を解雇して事実上休業状態となりました。
2021年11月には社有不動産を売却するなど整理を進め、2025年1月に福井地裁へ自己破産を申請。今回の措置に至りました。
[匿名さん]
当社は、1973年(昭和48年)12月創業、89年(平成元年)3月に法人改組された結婚式場・レストランの運営業者。福岡県大川市に本社を置くパン製造業者が、昭和48年12月に設置した結婚式場「ロイヤルパークアルカディアリゾート」(2012年5月閉館)の運営を足掛かりに、ブライダル事業に着手。ホテルの大型増築を機として(株)ロイヤルパークホテルの商号で分社化した経緯がある。以後は久留米市でのマンション建築による不動産賃貸をきっかけに同市内に進出。現本店となる「ロイヤルパークアルカディア久留米」は同地区初の本格的邸宅ウエディング形式の式場として人気を博していた。定期的な投資で、設備面の充実を図るほか、積極的な宣伝効果から知名度も向上。福岡県南部および佐賀県を主要商圏とし、北九州や福岡地区在住の結婚予定客からの申し込みも増えたことで「ウエディングワールドアルカディア小倉」「アルカディアSAGA」「THE アルカディア太宰府」を相次いで展開し、2013年8月期には年収入高約36億2100万円を計上していた。
その後、2013年9月には現商号へ変更。婚礼件数の減少に加えて、他地域からの競合施設の進出により、収入高は弱含みで推移していたなか、2015年には福岡市内にレストラン「QUANTIC」を出店。そのようななか、2020年に入ると新型コロナの感染拡大から、婚礼行事の中止・延期による影響で収入高は大きく落ち込んでいた。コロナ禍明けも業績の回復は難しく、2024年8月期の年収入高は約21億4000万円にダウン。最終損失は約5億2000万円にのぼり、約6億円の債務超過に陥っていた。この間コロナ関連融資などを調達する一方、これまでの設備投資に伴う借入金の返済が重荷になり、2023年5月に久留米市内の社有不動産を売却。さらに2024年3月には現代表に交代するなど立て直しを図っていたが、2025年2月に国の雇用調整助成金をだまし取ったとして元社長ら5人が逮捕されるなど対外的な信用は失墜し、先行きの見通しも立たなくなった。
負債は2024年8月期末で約40億3200万円だが、変動している可能性がある。
[匿名さん]
新聞用紙の生産量では国内4位だった製紙会社の丸住(まるすみ)製紙(愛媛県四国中央市)が28日、民事再生法の適用を東京地裁に申請した。東京商工リサーチ高松支社などが発表した。負債総額は約590億円という。関連会社2社も、同日付で民事再生法の適用を申請した。
ADVERTISEMENT
[匿名さん]
大分 NEWS WEB
大分の深掘り記事
去年の県内企業の倒産件数は69件 過去10年間で最多
03月04日 11時15分
去年の県内企業の倒産件数は69件と前の年より11件増え、過去10年間で最多となったことが民間の調査会社のまとめでわかりました。
民間の信用調査会社「帝国データバンク大分支店」によりますと、去年、1000万円以上の負債を抱えて倒産した県内企業の件数は69件で、負債総額は68億9400万円でした。
倒産件数が60件を超えるのは、2012年以来で、この10年間では最も多いということです。
業種別にみると、「小売業」と「サービス業」がそれぞれ15件で最も多く、次いで「建設業」が12件、「卸売業」が10件でした。
件数が増えた要因として、調査会社は、新型コロナに対応した実質無利子・無担保のいわゆる「ゼロゼロ融資」の返済が始まったことや、賃上げが進む中で人件費が上昇し、経営を圧迫したことなどがあると分析しています。
また、ネット通販を利用する人が増える中、従来の店舗型のビジネスモデルを脱却できずに経営が行き詰まったケースもあるなど、コロナ禍で変容した消費者の行動様式に対応できなかった企業が倒産するケースも相次いだということです。
今後の見通しについて帝国データバンク大分支店は、「物価高や円安に加えて、金利の上昇など、経営者を追い込む要素は多い。倒産する企業の数は増加傾向が続くとみられる」としています。
[匿名さん]
柏崎市の酒類販売店が破産申請の準備に入ったことがわかりました。
民間の信用調査会社、東京商工リサーチによりますと、柏崎市の「高橋節雄商店」は1956年に設立され、酒類の販売を主体に食料品の販売も手がけてきました。
しかし、ディスカウントストアやコンビニなどとの競争により売り上げ減少を強いられ、さらに2020年に時短営業や営業自粛で業績が低迷し、資金繰りが限界になったということです。
負債総額は約5000万円が見込まれています。
[匿名さん]
妙高市のホテルが新潟地裁高田支部から破産開始決定を受けたことが分かりました。
民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、妙高市の「ホテル十二屋」は1991年に赤倉スキー場近くに開業しました。
しかし、2019年ごろから資金繰りが苦しくなり、翌年に新型コロナが感染拡大するとスキー客が激減。業績低迷に歯止めがかからず、2024年3月にはホテルを売却し、その後事業も停止しました。
2月に新潟地裁高田支部から破産開始決定を受け、負債額は約2200万円が見込まれています。
[匿名さん]
副業で年収1千万円超オーナーも
IBJ
広告
PayPayポイントを確認
もっとみる
従業員「退職」で倒産、2024年は87件 過去最多を大幅更新
2518
コメント2518件
3/9(日) 7:01配信
帝国データバンク
「賃上げ」できない中小企業の淘汰、2025年に加速する可能性高まる
従業員が退職したことで事業継続を断念した倒産は過去最多を更新した(写真=イメージ)
人手不足が深刻となるなかで、従業員を自社につなぎとめることができずに経営破たんするケースが急増している。2024年に判明した人手不足倒産342件のうち、従業員や経営幹部などの退職が直接・間接的に起因した「従業員退職型」の人手不足倒産は87件判明した。前年(67件)から20件・約3割増加したほか、多くの産業で人手不足感がピークに達した2019年(71件)を大幅に上回り、集計可能な2013年以降で最多を更新した。
2024年の「従業員退職型」倒産を業種別にみると、最も多いのが「サービス業」(31件)で全体の35.6%を占めた。サービス業が全産業で最多となるのは、2019年以来5年ぶりとなった。特に多いのがソフトウェア開発などIT産業のほか、人材派遣会社、美容室、老人福祉施設など、いずれも人材の定着率が他産業に比べて低位になりやすく、人手不足感を抱える産業が中心となった。
次いで多いのが「建設業」(18件)で、設計者や施工監理者など、業務遂行に不可欠な資格を持つ従業員の退職により、事業運営が困難になった企業などが目立った。また、「製造業」や「運輸・通信業」では初めて年間10件を超え、工場作業員やドライバーの退職で事業がままならなくなったケースが相次いだ。
[匿名さん]
少子高齢化など人手不足が深刻化する中、従業員の退職が要因で経営破綻した企業数が昨年は87件で過去最多となった。帝国データバンクの調べで分かった。労働者の賃上げ要求が高まる一方で、待遇改善ができずに人材が流出する傾向は強まっており、今年はさらに倒産数が増える恐れが出ている。
帝国データバンクによると、令和6年の従業員や経営幹部の退職が直接的、間接的に起因した「従業員退職型」倒産数(負債1000万円以上)は87件で、5年の67件から20件増えた。増加率は約3割。平成25年の統計開始以降最多で、これまでは令和元年の71件が最多だった。
業種別では、サービス業が31件で全体の35%強を占めトップ。ソフトウエア開発などIT産業、人材派遣会社、福祉施設など人材定着率が低いためとみられる。次いで多かったのは建設業(18件)。設計や施工管理など業務に不可欠な資格保有者の退職が事業継続を困難にさせた。作業員や運転手の退職が響いた「製造業」と「運輸・通信業」が12件で続き、ともに年間10件を初めて超えた。
働き手の売り手市場となり、今後は人材流動性がより高まると見られ、賃上げなど待遇改善に消極的な経営で人材流出を招く「賃上げ難倒産」のリスクに対して、中小企業を中心に懸念が強まっている。
[匿名さん]
2月の全国の企業の倒産件数は700件を超え、2月としては4年連続で増加しました。人手不足関連の倒産が高水準となっています。
東京商工リサーチによりますと、2月の倒産件数【負債額1000万円以上】は764件で、去年より7.3%増えました。
倒産件数が前年を上回るのは去年9月から6カ月連続で、2月としては4年連続です。
また、負債総額は1712億7700万円【前年同月比22.6%増】でした。
資材やエネルギー価格の高騰により10の産業のうち8つの産業で倒産が増えた一方で、運輸業と小売業は減少しました。
人手不足関連の倒産は去年の12件から7件増えて19件でした。
そのうち人件費の高騰による倒産は10件で、去年の3件から3倍以上に急増しました。
[匿名さん]
背景には、「人手不足」「燃料価格の上昇」がある。人手不足を要因とした倒産(人手不足倒産)は、2024年度(11か月累計、全業種)で判明した308件のうち、道路貨物運送業者は38件で全体の12.3%を占めた。また、物価高を要因とした倒産(物価高倒産)は、2024年度(同)で判明した841件のうち、道路貨物運送業者は116件で13.8%を占め、そのうち9割が、「燃料価格の上昇」を要因としていた。人手不足・物価高(燃料高)のダブルパンチが深刻化していることが分かる。
2025年1月16日からのガソリン補助金縮小もあって、2月25日時点での軽油小売価格は164.0円と極めて高い水準にあり、先行きとしては厳しい環境が続く。
リーマン・ショック時も現在も軽油価格の高騰によるコストアップと収益悪化は共通している。一方で、当時は急速な景気減速を背景として荷動きの停滞が生じ受注難が発生していたが、現在ではアフターコロナでの消費回復もあって、一定の物流ニーズがありながらも、人手不足から受注が確保できていないという違いがある。
長期トレンドでみた労働人口減に加え、ドライバーの高齢化、人手不足が続く他業界との人材確保競争などもあるため、これらの課題解消に向けた賃上げなど、さらなるコストアップ要因も加わり、今後も道路貨物運送業の倒産は高水準で推移する可能性が高い。荷主と一体となった運送料金そのものの引き上げや、再委託構造の改善による価格転嫁率の上昇など、抜本的な対策が待ったなしの状況だとしている。
[匿名さん]
高森工業は1969年(昭和44年)創業、1990年(平成2年)設立の鉄鋼構造物の工事業者です。
富山県内を主な営業エリアとして工場の炉や架台の製作および取り付け工事などを手がけています。
最盛期とみられる2005年(平成17年)8月期には売上高約2億3600万円を計上していました。
その後は同業他社との競合で縮小傾向となり、2020年(令和2年)頃には主要な取引先が廃業したことで受注の落ち込みに拍車がかかりました。
2023年(令和5年)8月期には売上高4500万円まで落ち込むなどの苦戦を強いられ、下請け工事が主体となったことで採算の悪化による赤字経営が続いていました。
財務面での債務超過のなか資金繰りは切迫し、業務改善の見通しが立たなくなり今回の措置となりました。負債総額は金融債務を中心に約5000万円とみられます。
[匿名さん]
東京商工リサーチ新潟支店によると、家庭用金物、洋食器などの卸売を手がける株式会社酒井(新潟県燕市、設立1977年4月1日、資本金1,000万円、酒井一富社長、従業員4名)が3月13日付で弁護士名で貼紙を出し、事後処理を一任した。今後は破産による整理を予定している。負債総額は約7,000万円と見込まれる。
酒井は、1962年創業、1977年4月に法人化した家庭用金物、洋食器などの卸売業者で、県外企業を主体に販路を形成し、1997年3月期は約3億7,000万円を計上していた。
しかし、市況低迷や他社との競争激化などでその後は減収基調を余儀なくされ、2024年3月期の売上高は1億5,000万円程度に落ち込んでいた模様。また、採算的に恵まれない状況にあったほか、代表者の高齢化や従業員の退職などもあって事業継続は困難と判断し、破産申請に踏み切ることとなった。
[匿名さん]
新潟県長岡市の丸和自動車工業が新潟地裁長岡支部から破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました。
民間の信用調査会社・帝国データバンク長岡支店によりますと、丸和自動車工業は1969年に創業し、72年7月に法人改組された自動車整備業者で、地元長岡市の企業や一般個人から自動車整備や車両販売などの受注を確保し、95年6月期には年収入高約4000万円を計上していました。
しかし、限定された営業エリアでの小規模経営のため、業績は低調に推移。判明する2019年6月期の年収入高は約3000万円と、厳しい状況推移を余儀なくされていました。
こうした中、先行きの見通しが立たないことから、2020年頃には事業継続を断念したとみられ、今回の措置となりました。
負債は約1000万円に上っていたということです。
[匿名さん]
想定を超えるスピードで進む人口減。富山県の“最重要課題”についてシリーズで考えています。
【画像】“超加速”する人口減少に挑む富山・朝日町
去年、舟橋村をのぞく県内の自治体で初めて人口が1万人を割れた朝日町。
危機感が募る中、先月、衝撃の数字が示されました。
「直近のデータをもとに実態に応じた人口ビジョンに作り上げたいということで、今回新たに策定した」
3月27日に開かれた朝日町議会の全員協議会。
この場で町が示した35年後、2060年の人口予測は「2914人」。
過去10年間の転入・転出など人口移動平均でシミュレーションしたその数字に衝撃が走りました。
朝日町では県の人口移動調査に基づく推計人口が、去年9月1日時点で9984人と1万人を初めて下回りました。
舟橋村をのぞき、県内の自治体で人口が1万人を下回るのは朝日町だけです。
大村邦夫さん、87歳です。
町の中心部の商店街で64年間、和菓子店を営んでいます。
*大むら菓子舗 大村邦夫代表
「20〜30年ほど前から徐々に(店を)やめられていって、スーパーが出るようになってからですね。大型店が出るようになってから店が壊れ始めた」
町から消えていく商店。
客足が、年々減っていく様を目の当たりにしながら、大村さんは宮崎・境海岸で取れるヒスイをイメージした羊羹や観光名所「春の四重奏」をモチーフにした和菓子を作り続けています。
*大むら菓子舗 大村邦夫代表
「お菓子作りは好きだからやっている。いろんなお菓子を考えるのが面白い。人口が減るということは(和菓子を)食べる人がいなくなるので商売にならない。もっと人口が増えるような政策をとってもらいたい。それには企業で(若い人が)働く場所を
作ってもらいたい」
[匿名さん]
株式会社マイナビの調査では、2024年の上半期(1~6月)の間に退職代行サービスを利用して退職した人がいた企業は23.2%だった。2021年は16.3%、2022年は19.5%、2023年は19.9%と、年々増加傾向にあることが分かる。
【一覧】日本でこれから10年後に大きくなる会社、小さくなる会社【全業種342社】
「退職代行モームリ」を運営する株式会社アルバトロスによれば、そうした企業のうち約1割が、退職代行を複数回以上利用されている。なかにはなんと100回以上も使われた会社もあるというから驚きだ。
新年度初日となる1日には、134人が「モームリ」を利用。そのうち5件がなんと新卒の社員だった。2025年卒の新入社員からの依頼は、2日に8件、3日には20件と驚くべきペースで急増しているという。
“令和のブラック企業”像を探るべく、代表取締役・谷本慎二氏(36歳)に話を聞いた。
1位の企業は3年で100回以上も利用されている
「1位の会社は、モームリ創業から3年間で100回以上も利用されています。以前は10日に1回ほどのペースでしたが、最近また依頼者が一気に増えていて、数日に1度は連絡を入れているような状況です。退職代行でこれだけ多いということは、実際の退職者はこの100倍以上はいると考えられますので、とんでもない数にのぼると思います」(以下、「」は谷本氏)
図のランキングを見れば分かるように、モームリをもっとも使われたのはとある「人材派遣会社」だ。以降は第2位「コンビニチェーン」(65回)、第3位「人材派遣会社」(57回)、第4位「運送会社」(55回)、第5位「自動車販売会社」(49回)と続く。
「企業別に見ると、ほとんどの会社は1回のみ。全体の9.8%にあたる2667社が、少なくとも2回以上利用されている。40回以上利用された上位10社は、すべて従業員数が1500人を超える大企業です。主にファストフード店や保険会社、家電量販店など、サービス業が目立ちますね。長時間労働のうえ待遇が悪く、人間関係によるストレスや、キャリアの展望が見えづらいことが原因でしょう。
[匿名さん]
3月の倒産8件(富山)負債総額9億7300万円 件数、負債額とも前年上回るペース 帝国データバンク富山支店調べ
チューリップテレビチューリップテレビ
2025年4月2日(水) 17:33
3月の倒産8件(富山)負債総額9億7300万円 件数、負債額とも前年上回るペース 帝国データバンク富山支店調べ|TBS NEWS DIG
先月(2025年3月)の富山県内の企業倒産は8件で、前年同月から2件増加、前月比では横ばいとなりました。また負債総額は9億7300万円であることが帝国データバンク富山支店の調べでわかりました。
帝国データバンク富山支店によりますと、2025年3月の富山県内の負債額1000万円以上の倒産は8件で前の年の同じ月から2件増加しました。前の月とは横ばいになっています。
負債総額は9億7300万円で、前の月から6900万円減少しました。
業種別では「建設業」「製造業」「サービス業」が2件、「卸売業」が1件、が2件、「不動産業」が1件です。
主な原因は「販売不振」が4件、「放漫経営」が2件、「設備投資の失敗」が1件、「その他の経営計画の失敗」が1件です。
[匿名さん]
昨年度に東北6県で1000万円以上の負債を抱えて倒産した企業の件数は572件と、3年連続で前の年を上回り、東日本大震災以降で最も多くなりました。
信用調査会社の帝国データバンク仙台支店によりますと昨年度、東北6県で1000万円以上の負債を抱え、法的整理の手続きをとって倒産した企業の件数は、572件と前の年に比べて79件、率にして16%増加しました。
倒産件数が前の年を上回るのは3年連続で、東日本大震災以降、最も多くなりました。
業種別では▽建設業が146件と最も多く、▽サービス業が120件、▽小売業が115件などとなっていて、負債総額が最も大きかったのは、破産となった、盛岡市のパチンコホール運営会社のおよそ35億3500万円でした。
県別では▽宮城県が164件と最も多く、次いで▽福島県の117件、▽青森県の84件、▽山形県の81件、▽岩手県の80件、▽秋田県の46件となっていて秋田を除く5つの県で前の年よりも増加しました。
調査した会社は「今後の金利の動向やアメリカのトランプ政権の不確実性などの懸念材料も尽きないことから、今年度以降も倒産件数は緩やかに増加傾向をたどる可能性がある」としています。
[匿名さん]
前年度(32件)から1.6倍となり、これまで最も多かった2019年度の44件を上回った。洋菓子店の倒産増加が続いた2019年度までは、コンビニなどの安価で手軽なスイーツとの競争激化に耐えられず、市場からの撤退を余儀なくされたケースが多かった。2024年度は、原材料として使用量の多い小麦粉、鶏卵や砂糖、バターといった食材に加え、円安の影響を受けたナッツやフルーツ、カカオ不足で高値が続くチョコレートなど、主要な原材料や包装資材の仕入価格が高騰したことが影響した。
一般的なショートケーキ(ホール・18cm丸型)にかかる原材料コストを、店頭価格データなどを基準に「ケーキ原価」として算出した結果、原価は5年間で2割超上昇。チョコレートケーキの原価もカカオ不足の影響を受け5年間で約3割上昇し、ケーキの製造にかかわるコストの上昇傾向が続いている。ほかに、販売スタッフなどの人手不足、大手チェーンや近隣他店との競争激化なども加わり、厳しい経営環境となっているようだ。
[匿名さん]
2024年度の全国の企業倒産件数が11年ぶりに1万件を超えた。求人難や人件費高騰による人手不足倒産は前年度比で6割増え、過去最多となった。物価高による仕入れ価格上昇も中小経営を圧迫する。
東京商工リサーチは8日、24年度の全国企業倒産(負債額1000万円以上)が前年度比12%増の1万144件だったと発表した。東日本大震災の影響が残った13年度以来の1万件台となった。
中小・零細企業の倒産が多く、...
[匿名さん]
新潟県村上市で、とび工事業を営んでいた『稲葉工業』が1日に、新潟地裁新発田支部から破産手続き開始の決定を受けていたことがわかりました。
民間の信用調査会社である帝国データバンクや東京商工リサーチによりますと、村上市大場沢の『稲葉工業』は2001年に創業。主に新潟県内の同業者や建設業者からの下請けや一般個人宅からの受注を得て、土木構造物や各種建築物の足場工事を手がけていました。
2021年3月期には9417万円の年間売上高を計上しています。
ところが、若手従業員や外国人労働者の積極的な確保に努めた結果として人件費が上昇する一方で、2022年3月期以降は市況低迷のあおりを受けた売上低迷から赤字を連続計上し、債務超過も膨らんでいた模様です。
その後も年間で4000万円前半の売上にとどまるなど、販売不振から赤字が拡大して2025年2月末に事業を停止。外国人労働者も帰国し人手不足の解消もままならないなどの事情もあったとみられ、3月21日に自己破産を申請していました。
負債額は、約7180万円とみられています
[匿名さん]
民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、長野県箕輪町のザ・ミートと関係会社のメイマーズ、ワイエスが3月26日に長野地裁伊那支部から破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。
ザ・ミートは2011(平成23)年に設立された飲食店の経営業者で、フランチャイズチェーンに加盟し焼肉・鍋料理店を経営していました。
メイマーズは2007(平成19)年、ワイエスは2012(平成24)年に設立され、同じく焼肉・鍋料理店を経営し、松本市や伊那市、岡谷市、東京都八王子市、山梨県南都留郡などに出店していました。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げは減少、4店舗体制としていましたが収益も悪化して資金繰りはひっ迫。事業継続を断念し2024年5月ごろには店舗を閉鎖していました。
負債の内訳は判明していませんが、3社合計で約1億4000万円にのぼると見られています。
[匿名さん]
民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、長野県小川村でキノコ培地の原料となる「木ぬか」の卸事業などを営んでいた「おちあい」が、4月1日付で長野地裁に自己破産を申請したことがわかりました。
同社は1970(昭和45)年に設立され、当初は丸太や木材二次製品の卸を主体としていました。
1982(昭和57)年に同社が出資した長野木ぬか事業協同組合が設立されて以降は、キノコ生産者や農協などを顧客にキノコ栽培用の菌床の原料としての木ぬかの卸を主な事業として1999(平成11)年12月期の年間売上高は約2億4500万円を計上していました。
しかし、木材需要の低迷から木ぬかの調達が難しくなる中、競合は激化。熟成期間の短い低価格商品へのシフトが進んだことなどから売り上げは減少し、収益も悪化していました。
さらに、木ぬかの仕入れ先であった長野木ぬか事業協同組合と関連会社のホクサンが2024年6月に長野地裁から破産手続きの開始決定を受けた影響もあり、一段と業況は悪化。資金繰りがひっ迫して先行きの見通しも立たなくなり、事業の継続を断念したとみられています。
負債は約9000万円とみられています。
[匿名さん]
長野県山ノ内町のサービス付き高齢者住宅の入居者に介護・食事などを提供していた長野県岡谷市の企業が、4月に入り破産したことが分かりました。サービスを受けられなくなった利用者に不安が広がっています。
【動画で見る】「突然でショック…」サービス付き高齢者住宅で介護サービスを提供する企業が破産 約30人に介護や食事・入浴支援など実施 利用者に不安広がる 県「利用者の処遇を最優先に対応したい」
介護サービスを停止したのは、山ノ内町のサービス付き高齢者住宅「メディカル志賀」に併設された指定訪問介護事業所です。
長野県などによりますと、事業所を運営する「ヘルスケアセンター・メディカルタウン」(岡谷市)が、「メディカル志賀」を所有する企業から委託を受け、約30人の入居者に介護や食事・入浴支援などのサービスを提供していました。
しかし4月4日に「ヘルスケアセンター・メディカルタウン」から突然、利用者や職員に破産が告げられたということです。
利用者:
「突然だよね、それがショック。そんなやり方があるのかと。はじめのうちは年寄りに寄り添いなんて良いことばっかり豪語していたけど、後始末が悪すぎる」
県介護支援課は「事業者に義務付けられている事業停止1か月前までの届け出は無かった。突然のことで驚いている」とし、他の施設に協力を依頼するなど「利用者の処遇を最優先に対応したい」としています。
[匿名さん]
11日に発表された帝国データバンクの情報によりますと、青森県八戸市の(株)八光水産は、4月10日付で事業を停止し、事後処理を弁護士などに一任し、自己破産申請の準備に入ったということです。
▼ヤマダホームが事業停止・自己破産申請へ 負債約2億円
以下、帝国データバンクの発表した情報のほぼ全文となります。
(株)八光水産は、1998年(平成5年)8月設立の生鮮魚介類御売業者で、当地では後発ながら、イカ、サバを中心とした鮮魚の卸売、切り身や短冊などの一次加工も行い、ピ一ク時の2003年7月期には年売上高約13億1800万円の売上高を計上していたとしています。
その後は、イカ等の水揚げ不振を背景に漁期の短いイカを継続的に出荷出来るよう、冷凍凍結装置を導入したほか、サバの扱いも開始し、自社製品となる「八戸産しめさば」の製造販売も行っていました。
しかし、地元八戸港の水揚げ不振に歯止めがきかず、原材料確保に苦戦を強いられ、2024年7月期の年売上高は約2億8600万円まで落ち込み、原料や資材など製造コストの上昇を背景に赤字が続き、債務超過に陥っていたということです。
その後も業績改善の見込みが立たず、資金繰りが限界に違したことから、事業の継続を断念したとしています。
負債は、2024年7月期末時点で約1億4000万円(うち金融債務1億3000万円)。
[匿名さん]
1950年ごろにはダム建設の労働者が居住
村の発足当初に近い1950年の国勢調査によると、現在の村域の人口は8337人。電源開発のための平岡ダム建設の労働者が多く住み、この時がピークとみられる。その後、基幹産業の林業が衰退し、人口減少が続いている。
長野県で最も高い高齢化率
村によると、ここ数年は毎年40~60人ほどの減少が続いている。15~64歳の生産年齢人口の減少が就職や結婚による転出で著しい一方、今年3月末時点の65歳以上の高齢化率(61・42%)は県内で最も高い。
「ダム完成や林業衰退から立ち直れていないのでは」
村内で「買い物弱者」などを研究している長野大の相川陽一教授(農村社会学)は、天竜川下流の佐久間ダムを抱え、かつて林業で栄えた共通点を持つ浜松市天竜区佐久間町も同様の傾向があると指摘。「地元経済が、ダム完成や林業衰退当時の打撃から立ち直れていないと言えるのでは」と分析する。
[匿名さん]
新潟の経営者は考え方が50年遅れてんもんなぁ。
そりゃ若いのみんな出ていくわ。
エセ働き方改革で従業員をサイレントサビ残させ、経年劣化は頑として認めず、従業員に責任なすりつける。
そこらへんのとこ、某転職口コミサイトに事細かに書かれてるやんw
そりゃ何年も新卒入ってこないし、中途も来るわけねぇわなぁ、⭕️社さん?(´థ౪థ)
[匿名さん]
新潟県長岡市で旅行代理店を営んでいた『長岡ツアーズ』が、新潟地方裁判所長岡支部から8日に破産手続き開始の決定を受けていたことがわかりました。
負債額は約2400万円とみられています。
民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、1990年に設立された長岡市中島の旅行代理店『長岡ツアーズ』は、地元長岡市を中心とする中越地区近郊の個人・法人・学校を得意先として、2013年12月期には約4900万円の年売上高を計上していました。
しかし、限定された営業エリアでの小規模経営で業績が低調に推移するなかで、新型コロナウイルス禍以降の受注も伸び悩み、2023年12月期の年上高は約1200万円にまで落ち込むなど、厳しい経営を余儀なくされていた模様です。
その後、資金繰りも悪化し先行きの見通しが立たなくなったとみられています。
[匿名さん]
5月5日は「こどもの日」。新潟県がまとめた県内の14歳以下の子どもの数(4月1日時点)は21万5818人で、前年に比べ7795人減少した。県人口に占める子どもの割合は10・5%で、前年に比べ0・2ポイント低下した。県が統計の発表を始めた1981年以降、人数、割合ともに44年連続で減少し、最低を更新した。
内訳は男子が11万534人、女子が10万5284人。年齢別では、中学3年に当たる14歳が最も多く1万7999人。年齢が下がるとともに人数は減り、最も少ないのは0歳の9911人だった。
1981年は子どもの数が54万8059人で、県人口に占める割合は22・5%だった。81年以降、減少に歯止めがかかっていない。
花角英世知事は「急速に少子化が進んでいる。高校に...
[匿名さん]
新潟県でブラック企業が多く、低賃金で、人口が減少している背景には、いくつかの経済的・社会的な要因があります。以下に主な理由を挙げます:
---
1. 産業構造の問題
農業や製造業など低付加価値産業が中心で、賃金が上がりにくい。
大都市と比べてITや金融などの高収入業種が少ない。
2. 若者の流出
東京など都市部への進学・就職で若者が県外に出るため、人口減少が進行。
地元に戻るインセンティブが乏しく、Uターン就職が少ない。
3. 企業の体質
古い企業文化が根強く、長時間労働やサービス残業などの慣習が残っている。
労働者が声を上げにくい環境もブラック体質を助長。
4. 地方経済の停滞
地方経済が全国的に縮小傾向にあり、新潟もその影響を受けている。
需要の減少→企業のコスト削減→低賃金・過重労働という悪循環。
5. 公共政策や支援の不足
若者の定着や労働環境の改善に向けた政策が十分に機能していない。
県内企業の人材確保や育成への投資が不十分。
---
これらの複合的な要因が、新潟県における労働環境や人口動態に影響しています。
[匿名さん]
東京都中央区本社の大企業に内定貰った
転勤が東日本全域
取引先は大企業ばかり
下請け15000社
[匿名さん]
アホ幹部の若手社員を食い物にする社内不倫ばかりの風紀の乱れていた出版社、本当気持ちが悪すぎて、嫌悪感しかなかった、あほども
[匿名さん]
新潟の求人雑誌によく載ってる
滋賀・東近江労働基準監督署は、労働者2人について時間外労働の上限規制を超えて働かせたとして、ガラス製品の製造請負業のニチカレ㈱(滋賀県東近江市)と同社代表取締役を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで大津地検に書類送検した。1カ月当たりの時間外労働は最大で120時間を超えていた。
立件対象期間は、令和5年3〜5月。時間外労働の長さは平均して80時間を上回っていた。労働者2人は、元請会社の工場内で製造業務に従事していた。
同労基署は、長時間労働が発生していた要因について、「退職者が増え、人員が少ない状態だったようだ。増員を図っていたが人材を確保できず、残った労働者に負担が集中していた」と話している
[匿名さん]
携帯スマホショップもそうだしね
正社員1.2名で8割9割非正規
[匿名さん]
民間の信用調査会社東京商工リサーチによりますと、長野県木曽町で飲食店などを手掛けていた「武藤商事」が長野地裁松本支部から破産開始決定を受けました。
武藤商事は1980年に創業、飲食店を主体に贈答品の販売も手掛け、1995年12月期には売上高5000万円を計上していました。
しかし、以降は経営環境の変化から業績が悪化。
2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2023年12月期の売上高は260万円まで落ち込み、2000万円ほどの債務超過に陥ったということです。
事業再建のめどは立たず、2024年11月頃に事業を停止、今年3月末に自己破産を申請していました。
[匿名さん]
2025年4月の原材料高騰などに伴う「物価高」倒産は56件(前年同月比6.6%減)で、2024年11月から6カ月連続で50件以上で推移している。
負債総額は118億300万円(同20.1%減)と、2カ月連続で前年同月を下回った。
物価高は、競争力が弱く、価格転嫁が難しい小・零細企業の資金繰りを直撃している。物価高だけでなく、人件費上昇、金利引き上げなどが追い打ちをかけ、小・零細企業は厳しい状況に置かれている。
「物価高」倒産は、飲食店と食料品製造業が各6件、飲食料品小売業5件、飲食料品卸売業と持ち帰り・配達飲食サービス業が各4件と、商品関連の業種が上位に並ぶ。また、農業も3件発生し、食関連への影響が広がっている。こうした業種は、消費者向けの値上げは需要減、客数の減少に直結しかねず価格転嫁の難しさを示している。
形態別では、破産が52件(前年同月比1.8%減、構成比92.8%)。資本金別では、1千万円未満が33件(同3.1%増、同58.9%)で、5千万円以上はなかった。
2025年4月、トランプ米大統領が相互関税を打ち出し、円高推移をたどるが、コロナ禍前の水準には及ばない。さらに、人件費や金利引き上げも収益を圧迫し、物価安定の好転材料が乏しいなか、価格転嫁が難しい小・零細企業を中心にした「物価高」倒産は高止まりが続くとみられる。
※本調査は、2025年4月の企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、①仕入コストや資源・原材料の上昇、②価格上昇分を価格転嫁できなかった、等により倒産(私的・法的)した企業を集計、分析した。
[匿名さん]
 ポスト
ポスト